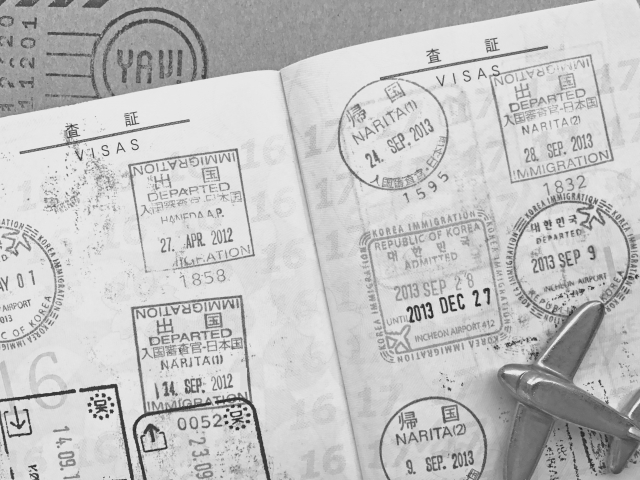〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分
特定技能
特定技能とは?

特定技能
ここでは在留資格『特定技能1号』および『特定技能2号』について解説していきます。
目次

特定技能で働く店員
在留資格『特定技能』は、特定産業分野にあたる日本の公私の機関と雇用契約を結んで働く外国人のための在留資格です。
出入国管理及び難民認定法(以下このページにおいて入管法)では、在留資格『特定技能1号』及び『特定技能2号』は以下のように定義されています。
特定技能1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定技能2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
解説
雇用契約の基準
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約については法務省令で基準が定められており、その基準に適合しないといけません。
特定産業分野
特定産業分野とは人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもので、以下のものが定められています。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
必要な技能
「特定技能1号」にある相当程度の知識又は経験を要する技能とは,当該特定産業分野における相当期間の実務経験等を要する技能をいい,当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
「特定技能2号」にある熟練した技能とは,当該特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい,当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。 なお,平成31年4月1日現在で,「特定技能2号」による外国人の受入れが可能となるのは,「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野となっています。
当該技能水準を有しているかの判断基準は,あくまで試験の合格等によって行われることとなります。よって,「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく,他方,試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
年齢に関するもの
18歳以上であること。
日本の労働法規では18歳未満の者に対して特別の保護規定が設けられています。これは外国人においても同様ですので、特定技能の外国人は18歳以上であることが求められています。
在留資格認定証明書交付申請は18歳未満でもできますが、実際に日本に入国できるのは18歳以上になってからです。
健康状態に関するもの
健康状態が良好なこと
特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保するため、当該外国人の健康状態が良好であることを求められています。
外国に在留している外国人が新たに日本に入国する場合(在留資格認定証明書交付申請を行う場合)には、申請の日から遡って3か月以内に、医師の診断を受ける必要があります。
技能実習生や留学生などで在留中の者が、「特定技能」へ在留資格を変更しようとする場合(在留資格変更許可申請を行う場合)には、申請の日から遡って1年以内に、日本の医療機関で医師の診断を受けて、その診断書があれば差し支えありません。
退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの
退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
退去強制令書の執行(退去強制処分)とは、不法就労や不法滞在などで日本にいる外国人を日本政府が強制的に外国人の母国等に送還することをいいます。自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。
平成31年4月1日時点で、協力しない国・地域として特定技能の外国人の受入れを認めていないのはイラン・イスラム共和国だけです。
保証金の徴収・違約金契約等に関するもの
申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられることがないように、この条件があります。
「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理」してはいけない機関等は、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、外国人の本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等も含まれます。
「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
費用負担の合意に関するもの
申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における準備に関して外国の機関に費用を支払ってい る場合には、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について,その意に反して徴収されることを防止するために,当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることが求められています。
費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提となりますが、旅券の取得等に要した費用など社会通念上、特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては、このルールにのっとって、外国の機関が費用を徴収することが求められます。したがって、特定技能所属機関が,職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て、特定技能外国人を雇用する場合にあっては、当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じて、次のとおり、合理的な費用でなければなりません。
- 食材、宅配弁当等の現物支給の場合は、購入に要した額以内の額
- 社員食堂での食事提供の場合は、従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額
- 食事の調理・提供の場合は、材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額
特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。
- 自己所有物件の場合は、実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
- 借上物件の場合は、借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については,実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
本邦に入国するに際して特定技能所属機関等に支払う費用について、特定技能外国人が、その額及び内訳を十分に理解した上で支払に合意していなければなりません。
特定技能所属機関は、入国後に当該外国人が定期的に負担する費用(住居費や食費等)について、その額及び内訳を十分に説明した上で、当該外国人から合意を得なければなりません。
特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用を控除する場合は、雇用条件書に控除する費用の名目及び額を確実に明記し、特定技能外国人が控除される費用の名目及び額を十分に理解できるようにしなければなりません。
定期に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には、特定技能外国人が生活する上で支障を来すことも考えられるため、徴収する金額は、実費に相当する等適正な額でなければなりません。その費用額が高額である場合には、実費に相当する等適正な額であることについて疑義が生じることから,場合によっては追加的な立証が必要となります。
上記の同意に関する書類は、すべて特定技能で働く外国人本人が十分に理解できる言語により作成し、外国人本人がが内容を十分 に理解した上で署名することが求められます。
本国において遵守すべき手続きに関するもの
申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続が行われている必要があります。
分野の特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
その他、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
特定産業分野によっては別途条件が追加されているものもあります。それらの別途定められている条件にも適合していないといけません。
技能実習2号を良好に修了した場合
技能実習2号を良好に修了し、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、(特定技能の在留資格で)従事しようとする業務において必要な技能と関連性が認められる場合特定技能1号の在留資格を得る際の条件の一部が免除されています。
技能実習2号を良好に修了した場合とは
次の条件を満たしている必要があります。
- 技能実習を2年10か月以上修了していること。
- 次のどちらかを満たしていること
- 第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験 (専門級)の実技試験に合格していること
- 技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの,特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況,生活態度等を記載した評価に関する書面により,技能実習2号を良好に修了したと認められること
免除される条件
免除される条件は以下の2つです。
- 技能水準に関するもの
- 日本語能力に関するもの
日本語能力に関するものについての注意点
介護分野において証明を求めることとしている介護日本語評価試験の合格については、介護職種・ 介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除されません。
技能水準に関するもの
従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法によ証明されていること。
1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求められています。
試験その他の評価方法については特定技能分野により違います。詳しくはお問合せください。
日本語能力に関するもの
本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
1号特定技能外国人について、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求められています。
通算残留期間に関するもの
特定技能の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留 した期間が通算して5年に達していないこと。
特定技能1号の在留資格で在留することが出来るのは5年間だけです。特定技能雇用契約期間や在留期限が残っていても5年になると以後の在留は認められません。
次の期間も通算されます。
- 特定産業分野を問わず(他の特定産業分野によるものであっても)、今までに在留資格『特定技能1号』日本に在留した期間
- 失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
- 労働災害による休暇期間
- 再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
- 「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
- 平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
技能水準に関するもの
従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
『特定技能2号』の技能水準は『特定技能1号』より高度な技能を有している必要があり、試験その他の評価方法で証明されている必要があります。
また「『技能実習2号』を良好に修了していても」免除されません。
技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの
技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
技能実習制度の本来の目的は、実習生が技能を習得して、その技術を本国へ移転して本国の技術向上に貢献するためのものです。
技能実習の活動に従事していた者が「特定技能2号」の許可を受けようとする場 合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めないといけません。
「努めるものと認められること」とは、本邦で修得等した技能等の本国への移転に努めることが見込まれることをいい、実際に本国への移転を行い成果を挙げることまでを求めるものではありません。
「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者」には、「技能実習」の在留資格が施行された平成22年7月前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた者も含まれます。
従事させる業務に関するもの
相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
1号特定技能外国人については、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として、2号特定技能外国人については、熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
所定労働時間に関するもの
外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
報酬等に関するもの
外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
一時帰国のための有給休暇取得に関するもの
外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求められています。
既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。
派遣先に関するもの
外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。 )の対象とする場合にあっては,当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として 雇用する場合は,当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていることを求めるものです。
2019年3月20日現在、特定技能外国人を派遣形態で雇用することが出来る分野は、「農業分野」及び「漁業分野」のみです。とされていることから、これ以外の特定産業分野については、特定技能外国人を派遣形態で雇用することは認められません。
「労働者派遣とは」(参考条文)
「労働者派遣」とは、次のものをいいます。
労働者派遣法第2条第1号
自己の雇用する労働者を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために労働に従事させることをいい,当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。
船員職業安定法第6条第11項
この法律で「船員派遣」とは,船舶所有者が,自己の常時雇用する船員を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために船員として労務に従事させることをいい,当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。
帰国担保措置に関するもの
外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。
「旅費を負担することができないとき」とは、特定技能外国人が自ら帰国費用を負担することができない場合をいい、帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問いません。
「必要な措置」とは、帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約及び購入を行うなどを含む措置を講ずることをいいます。
特定技能所属機関は、経営上の都合等により帰国費用を負担することが困難となった場合に備えて第三者(登録支援機関や関連企業等)と協定を結ぶなどしておくことが望まれます。
帰国旅費を確保しておくために、特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特定所属機関が管理することは、金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから、認められません。
健康状態その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの
特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
「健康状況の把握のための措置」とは、労働安全衛生法に定める雇入れ時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施すること、健康状況に問題がないかを定期的に特定技能外国人から聞き取りを行うなどの措置を講じることをいいます。
「その他の生活の状況の把握のための措置」とは、緊急連絡網を整備したり、定期的な面談において、日常生活に困っていないか、トラブルに巻き込まれていないかなどを確認することをいい、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援とともに実施していただいても差し支えありません。
労働、社会保険及び租税に関する法定の規定を遵守に関するもの
労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
特定技能外国人として日本で労働する方は日本の労働者災害補償保険の適用をうけます。そのため、特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していなければいけません。
「その他これに類する措置」とは、特定技能所属機関が労災保険制度において暫定任意適用事業とされている農林水産の事業の一部を想定しているもので、この場合、労災保険の代替措置として、労災保険の任意加入や、労災保険に類する民間保険に加入していることをいいます
非自発的離職者の発生に関するもの
特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。
- 定年その他これに準ずる理由により退職した者
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
- 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
- 自発的に離職した者
特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められています。
「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは、特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者、中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない。)をいい,特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者をいいます。
「非自発的に離職させた」とは、具体的には次のものに該当する場合をいいます。なお、非自発的離職者を1名でも発生させている場合は、基準に適合しないこととなります。
- 人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生によりやむを得ず解雇する場合は除く。)
- 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
- 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合
- 特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
行方不明者の発生に関するもの
特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと。
「外国人」とは、受け入れた特定技能外国人をいい、また、実習実施者として受け入れた技能実習生も含まれます。
「責めに帰すべき事由」があるとは,特定技能所属機関が、雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など、法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます。そのような法令違反や基準に適合しない行為が行われていた場合には、人数に関係なく、特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば、本基準に適合しないこととなります。
特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の実習実施機関を含む。)として、特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又は締結の日以後に、受け入れた技能実習生について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも、本基準に適合しないこととなります。
行方不明者を発生させた特定技能所属機関が、基準に適合しないことを免れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、当該別会社も行方不明者を発生させた機関として、取り扱うことがあり得ます。
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を適切に履行するだけでなく、特定技能外国人からの相談に真摯に応じ、当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし,外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。
支援に要する費用の負担に関するもの(特定技能1号のみ)
法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動(特定技能1号の活動)を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること。
1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、本制度の趣旨に照らし、特定技能所属機関等において負担すべきものであることから、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。
「支援に要する費用」とは、1号特定技能外国人に対して行われる各種支援(特定技能基準省令第3条に定める「義務的支援」)に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。)をいい、次のものを含みます。
- 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等
- 1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等
なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。
1号特定技能外国人の受入れに当たっては、事前ガイダンスにおいて、支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明してください。また、生活オリエンテーションにおいても、同様に説明してください。(特定技能外国人に十分理解できる言語において)
欠格事由に関するもの
事業主が、次の条件に当てはまる場合はを特定技能所属機関になることは出来ません。
事業主が個人事業主の場合は代表者が、法人の場合は役員が該当している場合があてはまります。
関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由
次のいずれかで刑罰を受けた場合は、「刑に処せられ,その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ た日から5年を経過するまで」欠格事由となります。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
- 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
- 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑 に処せられた者
特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由
次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。
- 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
実習認定の取消を受けたことによる欠格事由
実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)。
欠格事由の対象となる役員については、法人の役員に形式上なっている者のみならず、実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者のことをいいます。
出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことによる欠格事由
定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に,次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(1)外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為
(2)外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
(3)外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
(4)外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為
(6)外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節 若しくは第2節の規定による証明書の交付,上陸許可の証印若しくは許可,同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で,偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,又は提供する行為(偽変造文書等の行使・提供)
(7)特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為(保証金の徴収等)
(8)外国人若しくはその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて,当該外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為(違約金を定める契約等)
(9)法第19条の18の規定(特定技能所属機関による届出)による届出をせず,又は虚偽の届出をする行為
(10)法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避する行為(報告徴収に対する妨害等)
(11)法第19条の21第1項の規定による処分(改善命令等)に違反する行為
(1)外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為
外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行っている場合をいいます。なお、当該行為によっ て刑事罰に処せられているか否かは問いません。
(2)外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
外国人の旅券や在留カードを、その意思に反して保管している場合をいいます。例えば、 特定技能所属機関において失踪防止の目的などとして、旅券や在留カードを保管していた場合が該当します。(なお特定技能外国人は在留カードを常時携帯する義務があります)
(3)外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
外国人に対し、手当若しくは報酬の一部又は全部を支払わない場合をいいます。 「手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為」とは、不払金額、不払期間、事業主の認識等を勘案して評価されます。なお、食費・住居費等を天引きしている場合であっても、天引きしている金額が適正でない場合には、本欠格事由に該当する可能性があります。
(4)外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
外国人の外出、外部との通信等を不当に制限している場合をいいます。例えば、携帯電話を没収するなどして、外部との連絡を遮断するような行為が該当します。
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為
外国人の人権を著しく侵害する行為(上記(1)から(4)までの行為を除く。)を行っていた場合をいいます。例えば、特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合等が該当します。
(6)偽変造文書等の行使・提供
外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印若しくは在留資格変更許可等を受けさせる目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場合をいいます。例えば、在留資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出したところ、じ後、地方出入国在留管理局の調査によって当該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当するので、申請及び届出においては、事実関係の確認を十分に行う必要があります。
(7)保証金の徴収等及び(8)違約金を定める契約等
外国人やその親族等から保証金を徴収している場合、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定めている場合等や、これらの行為を行っている者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締結した場合をいいます。例えば、特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めていた場合が該当します。また、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等に対して不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や特定技能外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。
(9)法第19条の18の規定(特定技能所属機関による届出)による届出をせず,又は虚偽の届出をする行為
法令上規定する届出事由が生じていながら、地方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合をいいます。例えば、特定技能外国人が行方不明になったにもかかわらず、これを届け出ることなく、失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて、行方不明になっていたことが明らかになった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかかわらず、これを履行しない場合等が該当します。
(10)報告徴収に対する妨害等
法第19条の20第1項の規定により求められた報告や簿書類の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだり妨害した場合等が該当します。
(11)法第19条の21第1項の規定による処分(改善命令等)に違反する行為
出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合をいいます。
その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為
主に以下の行為です。
- 不法就労者の雇用
- 労働関係法令違反
- 技能実習制度における不正行為
- 他の機関が不正行為を行った当時に役員等として外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為
暴力団関係者に対する欠格事由
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
次に該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。
- 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及びその役員が暴力団員等
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由
特定技能雇用契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合、又は、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該特定技能雇用契約を締結していないこと。
他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。
特定技能所属機関は、特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないことを求めるものです。
「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、管理する主体が特定技能所属機関、登録支援機関、職業紹介事業者など特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本邦外の仲介事業者(ブローカー)等を含まれます。
「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
派遣形態による受入れに関するもの
外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては,次のイ、ロいずれ にも該当すること。
イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が,次のいずれかに該当し,かつ,外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。
(1)当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。
(2)地方公共団体又は(1)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。
(3)地方公共団体の職員又は(1)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は(1)に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。
(4)外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては, 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
ロ・外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が,第1号から第4号 までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしている こと。
特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には,派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求められるほか,出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。
派遣先についても,派遣元である特定技能所属機関と同様に,労働,社会保険及び租税に関する法令の遵守,一定の欠格事由に該当しないことなどを求められています。
特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの
特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
特定技能所属機関に,特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため,特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることを求めるものです。
特定技能雇用契約を継続して履行する体制として,特定技能所属機関が事業を安定的に継続し,特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。
報酬の口座振込み等に関するもの
特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を,当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該外国人に現実 に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており,かつ,当該預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によって報酬の支払をした場合には,出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し,出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。
特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため,当該外国人に対し,報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上で,当該外国人の同意を得た場合には,預貯金口座への振込み等により行うことを求めるものです。
預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合には,じ後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し,出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。
日本国外にいる外国人を呼び寄せる場合はまず在留資格認定証明書交付申請を行い、発行後外国人本人に外国の大使館等に査証(ビザ)の申請を行います。査証が下りたら日本に来ていただくことになります。
『特定技能1号』『特定技能2号』での在留資格認定証明書交付申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
必要書類一覧
必要となる書類、添付資料は『特手技能1号』『特定技能2号』ともに、特定技能所属機関の形態(法人・個人)や雇用形態(直接雇用・派遣雇用)によって違います。以下のリンクより対応したファイルをダウンロードしていただくようお願いいたします。
出典元:法務省ウェブサイト特定外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表より
※ファイルは、PDF形式となっております。開けない場合は、Adobe Readerをインストールしてください。
現在他の在留資格で日本に滞在している外国人が、『』に在留資格を変更するためには在留資格変更許可申請を行います。
『特定技能1号』『特定技能2号』での在留資格変更許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
必要書類一覧
必要となる書類、添付資料は『特手技能1号』『特定技能2号』ともに、特定技能所属機関の形態(法人・個人)や雇用形態(直接雇用・派遣雇用)によって違います。以下のリンクより対応したファイルをダウンロードしていただくようお願いいたします。
出典元:法務省ウェブサイト特定外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表より
※ファイルは、PDF形式となっております。開けない場合は、Adobe Readerをインストールしてください。
現在『特定技能1号』『特定技能2号』で在留する外国人の方で、在留期限後も引き続き同じ在留資格で在留するためには在留期間更新許可申請を行います。
『特定技能1号』『特定技能2号』での在留期間更新許可申請について必要な書類について解説いたします。なお外国人本人や呼び寄せる予定の日本人、企業等によって追加の必要書類が必要な場合があります。また当事務所で作成、収集が出来る書類もあるので詳しくはお問い合わせください。
必要書類一覧
必要となる書類、添付資料は『特手技能1号』『特定技能2号』ともに、特定技能所属機関の形態(法人・個人)や雇用形態(直接雇用・派遣雇用)によって違います。以下のリンクより対応したファイルをダウンロードしていただくようお願いいたします。
出典元:法務省ウェブサイト特定外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表より
※ファイルは、PDF形式となっております。開けない場合は、Adobe Readerをインストールしてください。
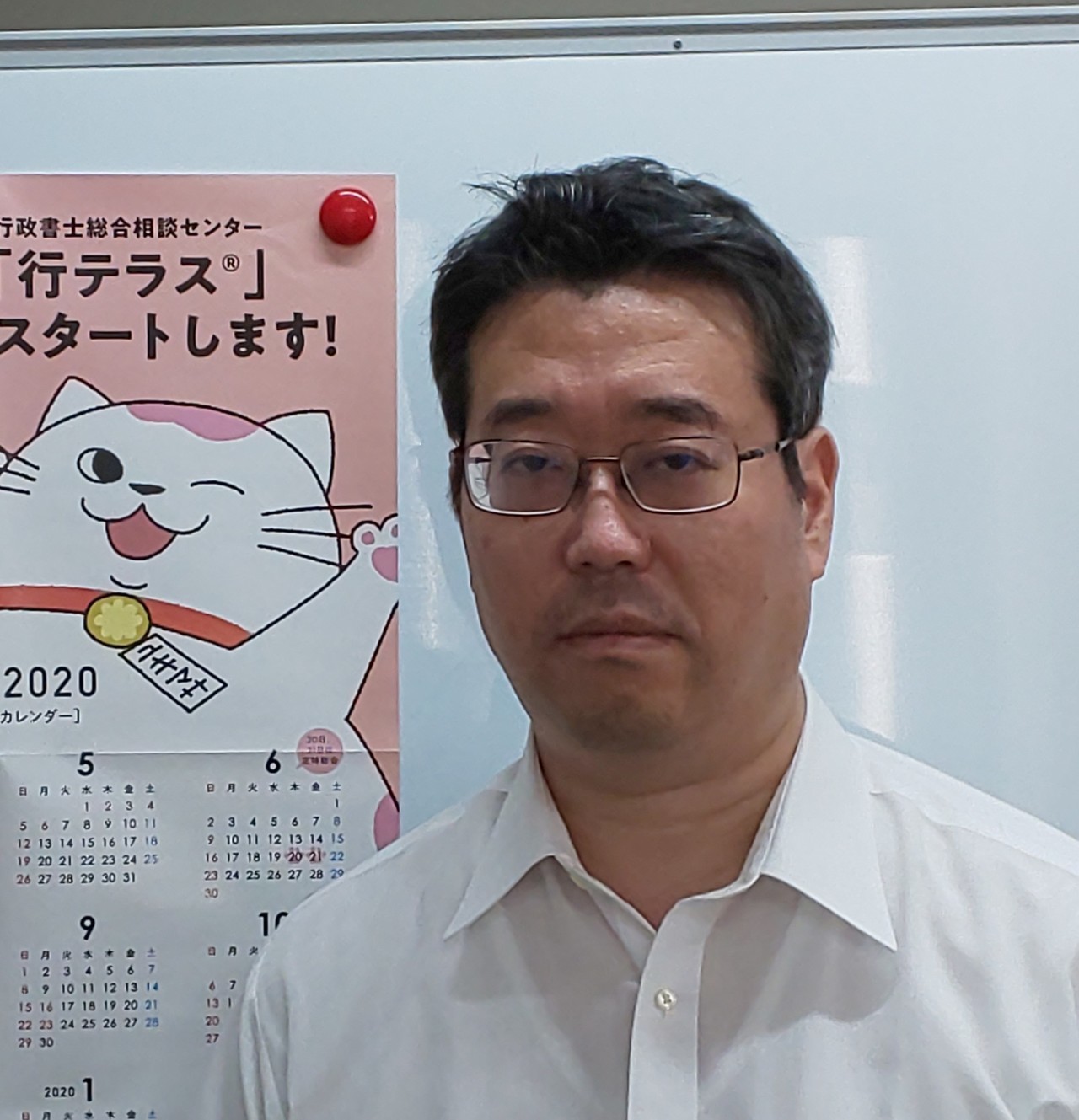
谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
あなたのお悩みを解決します!
具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。
私は申請取次行政書士として皆様の代わりに外国人の在留手続きを行うことが出来ます。
在留資格に関する手続き

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら
電話によるネット集客営業の電話はご遠慮ください。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
INFORMATION
お客さまの声
丁寧な対応に安心

30代女性 Aさま
谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
お勧めしたいサービス

40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。