〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティー元町 511号室
神戸市営地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩5分
遺言書の作成支援
遺言書について
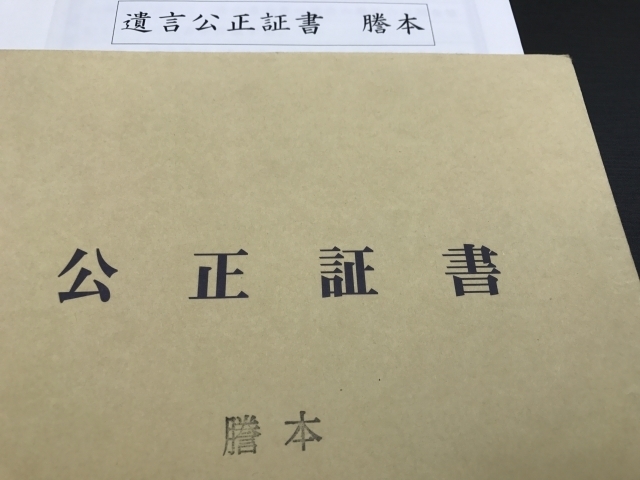
遺言書
ここでは遺言書の作成及び当事務所での作成支援について解説をしていきます。
目次
遺言書は自分が死亡した後、自分の財産を誰に相続させるかを自分で指定出来る唯一の方法です。
遺言書を作成せずに死亡した場合は、遺族が遺産の分割協議をして相続配分が決まることになります。したがって自分の思うとおりの相続の分け方になる保証はありません。
ご自分が亡くなった後、遺族同士の争いがおき、自分が望んでいた遺産分割にならなかったという事態に陥らないように遺言書の作成を支援いたします。
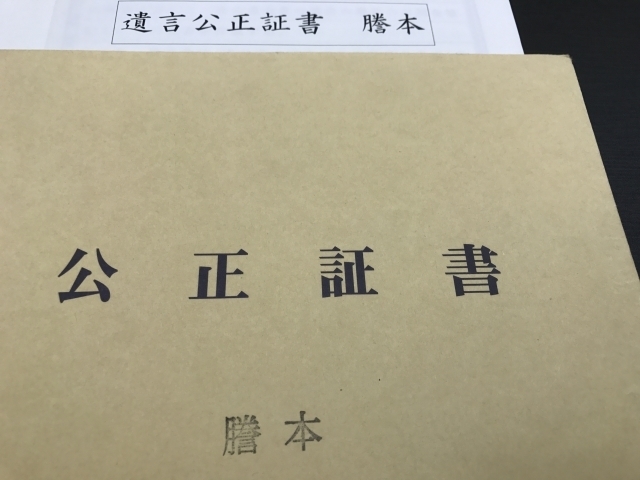
いろいろな遺言
目次
遺言は通常、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。その他特別な方式のものとして認められたものもあります。(民法967条)
自筆証書遺言の作り方
自筆証書遺言は紙に書く必要があります。音声や映像のデータ、パソコンやスマホ等の端末データ、印刷された物(目録部分を除く)はすべて無効として作成されなかったものと扱われます。書く内容についても、以下の4つの条件すべてそろっていないといけません。
- 1目録を除く全文(誰にどんな財産を相続させるか)を自分で書く
どの財産を誰にどれだけ分けるかは自分で決めて書く必要があります。
- 2日付を自分で書く
遺言の作成回数に制限は無く、複数回作成することも出来ます。作成者の死後、複数の有効な遺言が発見された場合、後から作成された遺言が優先されます。したがって、日単位で作成日が特定できないと優先度がわからなくなるため日付が必要になります。作成日が特定されればいいので元号表記でも西暦でもどちらでもかまいませが、例えば令和元年12月吉日という表記では特定できないため無効になります。
- 3自分の名前を自分で書く
誰の遺言書かわからないといけないので署名をします。
- 4ハンコを押す
最後に押印がなければいけません。
財産目録をパソコン等で作成する際の注意点
自筆証書遺言を作成する際、本文は自分で書いて作成する必要がありますが、相続財産の全部又は一部の目録(以下財産目録)を添付するときは、その財産目録については自分で書く必要はありません。但し、その場合でもいくつか注意事項があります。
- 財産目録を作成した場合、本文に「別紙財産目録1をAに遺贈する。」「別紙財産目録2をBに遺贈する」といったように記載して、別紙としてパソコン等で作成した財産目録をそれぞれ添付することが出来ます。しかし本文のほうは全文を自分で書く必要があります。
- 自書によらない(自分で書いていない)財産目録を添付する場合には、そのページそれぞれに署名訪印をしなければいけません。また両面印刷等をして両面にある場合は両方に署名押印をしなければいけません。
- 署名押印以外の書式は自由です。パソコン等で作成することも出来ますから、遺言者以外の人が作成することも出来ることになります。その他不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付することも出来ます。
- 本文と財産目録をステープラー等で閉じたりする必要はありませんが、本文と一貫性を保つ措置を取っておくことをお勧めします。また自書によらない財産目録と本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成しなければならず、同一の用紙に両方を記載することは出来ません。
自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言は自分で保存をする必要があります。盗難等に注意する必要があります。また作成や保存場所を誰にも告げなかった場合、死後発見されずに相続が法定通りに終わる可能性もあります。
自筆証書遺言遺言を見つけたら・・・
例えば遺品を整理していた時に、亡くなった方の自筆証書遺言が見つかったら・・・
やってはいけないことがあります。
- 1封をしている場合は封を自分で開封してはいけません。
自筆証書遺言を見つけたら、見つけた人が家庭裁判所に持って行って検認手続きというものをしないといけません。(民法1004条第1項)
この検認手続きの過程で封をはがすため、その前に封をはがしてはいけません。
(同条第3項、1005条)
- 2遺言の存在を隠したり、捨てたり、燃やしてはいけません。
例え自分に不利な遺言書であっても遺言書をなかったことにしてはいけません。もし捨てたり燃やしたりした場合はその人には遺産は1円も相続されません。(民法891条第5号)
公正証書遺言は公証人の方及び証人2人の立ち会いのもとに作成して、公証役場で保管される方式の遺言です。作成する際は専門家の公証人と共に作成され、遺言者の死後に形式の不備によるトラブルが非常におこりにくいです。また保管は公証役場でされるため、紛失や盗難のリスクもありません。公証人に支払う報酬等で自筆証書遺言より費用はかかりますが、作成後のことを考えこちらの作成方法をお勧めします。
遺言書作成のメリット
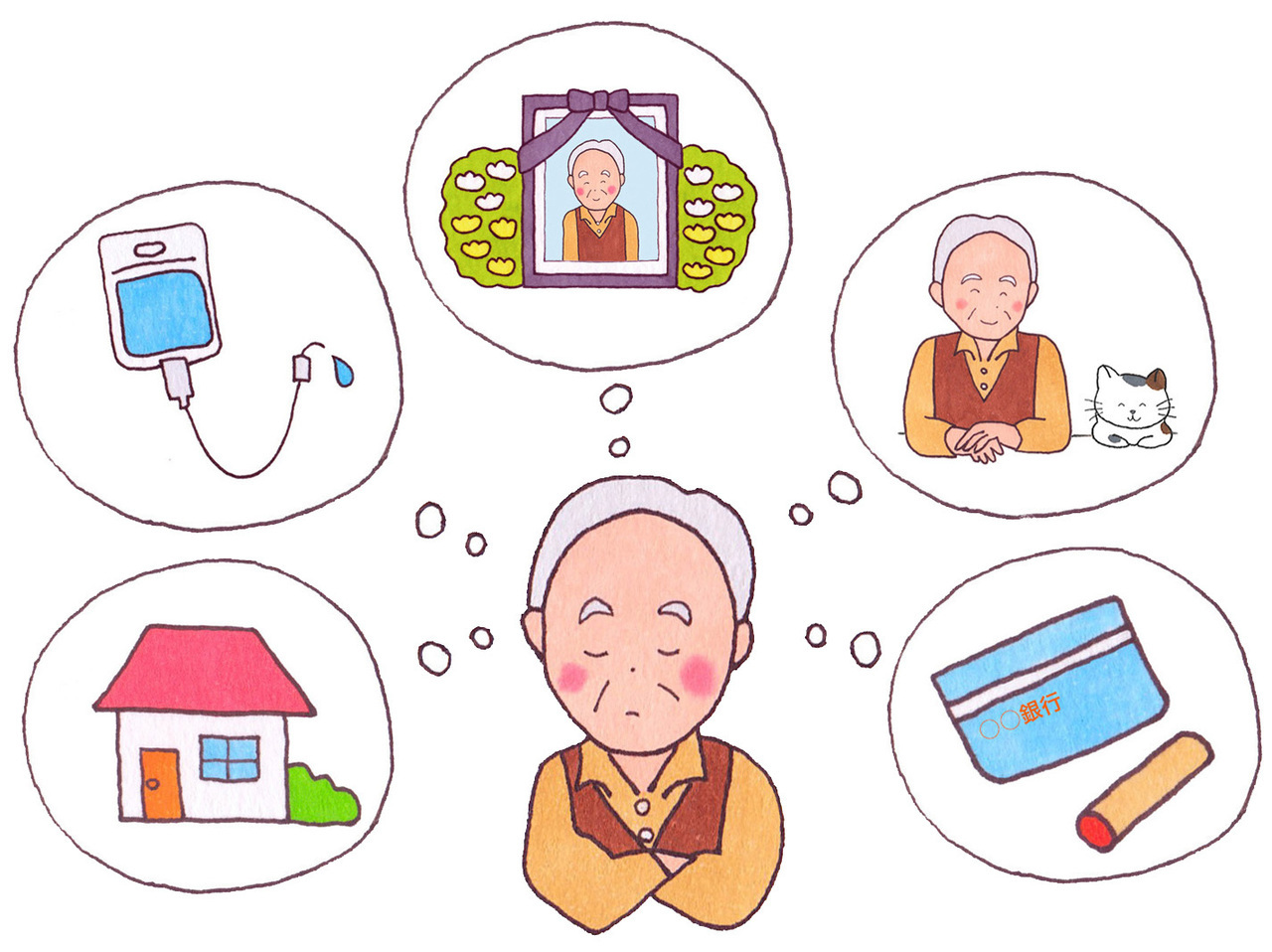
上述したように遺言書は自分の死後に自分の財産の相続を決めることの出来る唯一の方法です。
遺言書を作成しないと自分の思うとおりの相続にならなくなります。
このような場合は是非遺言書を作成しましょう。

このような人は遺言書を作成しないと、自分の死後トラブルになる可能性があったり、思うとおりの相続にならなかったりするので、遺言書の作成を特にすすめます。
お子様、お孫様がいない方
このような方は自分の死後、親や兄弟姉妹、甥、姪が相続に関わることになり、関係が複雑になります。その結果相続人同士の話し合いがこじれる可能性が高くなります。遺言書を作成することによって、話し合いの過程をスキップすることが出来るので、非常に有用な手段になります。
相続の配分に不満を持ちそうな家族がいる方
残された遺族による話し合いは、相続人になる方全員の同意が無いと成立しません。一人でも話し合いによる相続分割を拒否したり、話し合った分割内容に不満があり同意をしなかった場合はそれまでの話し合いがすべて無駄になります。事前に遺言書を作成することで、残された家族がこのような苦労をしないようにすることが出来ます。
ご家族の中に今の居場所がわからない人がいる方
先に述べたように相続人全員の同意がないと遺産分割は終わりません。居場所がわからない、連絡が取れない家族がいる場合そもそも話し合いを始めるところから難しくなります。
自分の財産の中に分けるのが難しいものがある方
自分の財産の中に不動産(土地や建物)がある場合、それも相続財産になるので分割時に複数人の共有になってしまい、処分等が難しくなる可能性があります。遺言書によって相続する人を指定することによって、分割されることなく相続させることが出来ます。また株券等も特定の人を相続人にすることによって事業の継承がうまくいくことになります。
相続人以外の方に財産を贈りたい方
法律によって決められた相続人は配偶者や子などの親族に限られており、それらの相続人以外の方で特にお世話になった方とかに財産を残したい場合は、遺言書を作成しないと相続人の中に入ることが出来ません。特別に財産を贈りたい方がいる場合は必ず遺言書を作成しておきましょう。
| 公正証書遺言作成支援※1 | 40,000円 |
|---|
| 自筆証書遺言作成支援 | 40,000円 |
|---|
費用はすべて税別です。
ご相談内容、お客様の状況によって金額が変わる場合があります。事前の見積もりをいたします。
※1公正証書遺言の作成には当事務所への報酬の他に公証役場において支払う手数料が別途かかります。
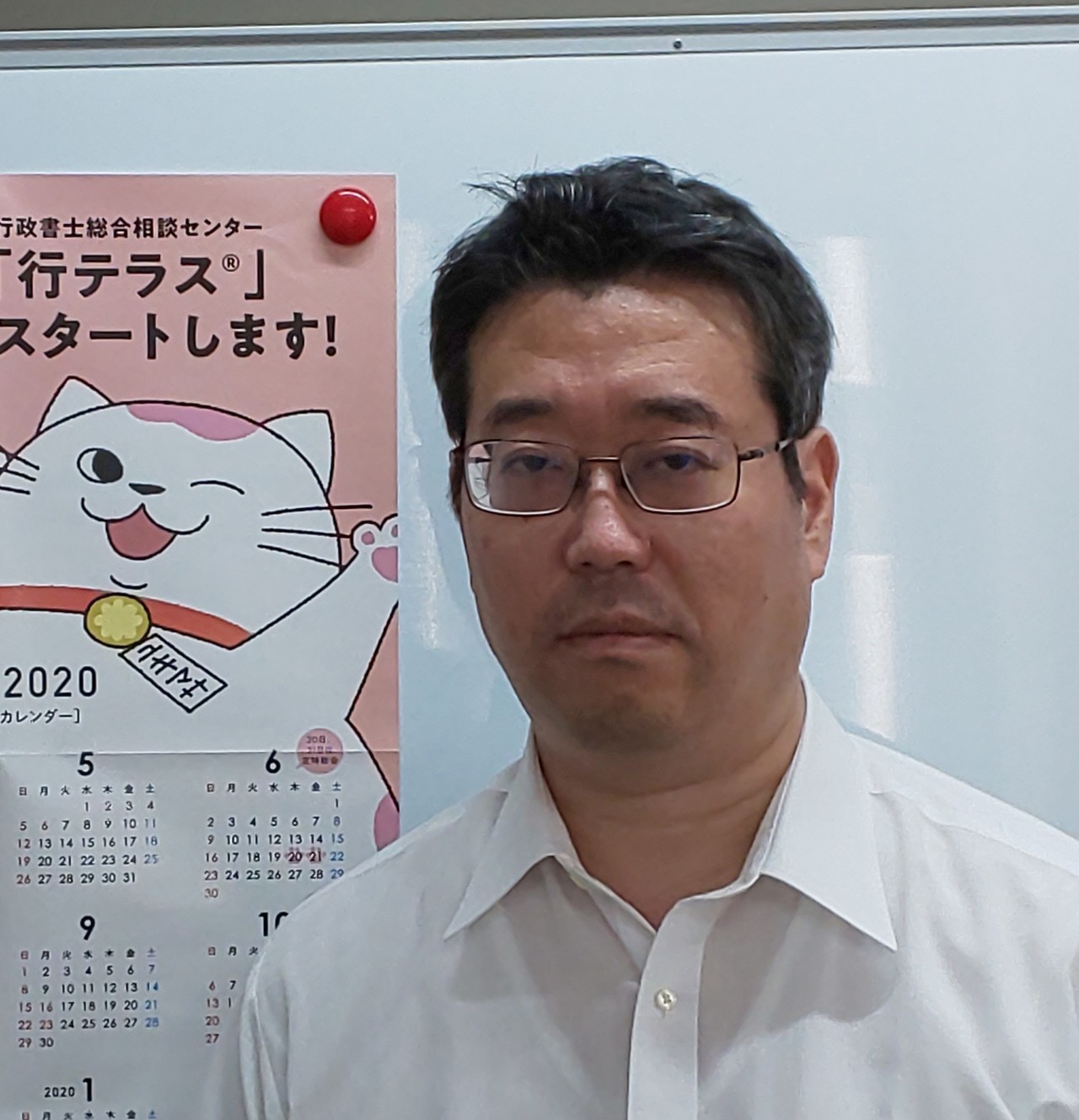
谷野行政書士事務所代表の
谷野 学です。
あなたのお悩みを解決します!
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺言書作成支援サービスなら、皆様の相続に関する不安が解消されます。
遺言書の作成に興味をお持ちの方。具体的な手続きでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら
電話によるネット集客営業の電話はご遠慮ください。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
INFORMATION
お客さまの声
丁寧な対応に安心

30代女性 Aさま
谷野行政書士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
お勧めしたいサービス

40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ谷野行政書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。

